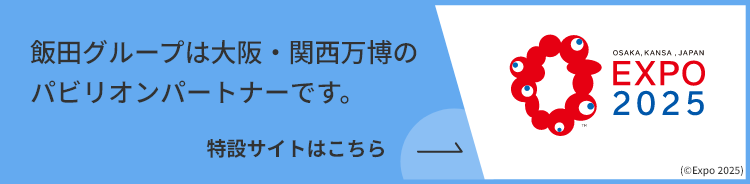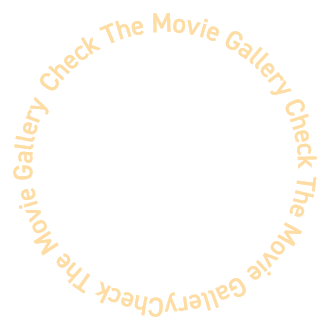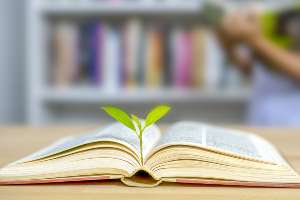人生100年時代を、
すまいで支える。
「私たちでも家を買えるのかな?」
「“人生100年時代”に安心して住める家がいい」
すべてはそんな疑問や思いを持つあなたのために。


スケールメリットによる好価格と、厳しい基準をクリアした高品質。
これらを満たす家を年間約40,000戸以上提供しているシェアNo.1実績。
たくさんの家を建ててきたからこそ、できることがある。
それが私たちの誇りと約束です。